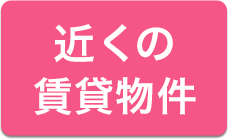「HIS アバンティ&オアシス金沢店」から直線距離で半径1km以内の神社・寺院を探す/距離が近い順 (1~20施設)
①施設までの距離は直線距離となります。目安としてご活用ください。
②また ボタンをクリックするとHIS アバンティ&オアシス金沢店から目的施設までの徒歩経路を検索できます。
ボタンをクリックするとHIS アバンティ&オアシス金沢店から目的施設までの徒歩経路を検索できます。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 尾山神社は、石川県金沢市に位置する歴史的で文化的にも重要な神社で、観光地としても非常に人気があります。ここでは、尾山神社の魅力をいくつかの視点から紹介します。 まず、尾山神社は金沢の歴史に深く根ざした場所です。神社は、加賀藩初代藩主である前田利家公を祀るために創建されました。利家公は、豊臣秀吉に仕えた名将であり、加賀藩の礎を築いた人物です。神社には利家公とその妻であるまつ(まつ姫)の霊を鎮めるための本殿があり、歴史的にも重要な意味を持つ場所として、多くの参拝者が訪れます。 尾山神社の最大の魅力の一つは、その建築様式です。特に「尾山神社の楼門」は、金沢市の象徴的な建物の一つとして有名です。この楼門は、前田家のシンボルである「三つ葉葵」の紋をあしらったデザインが特徴的で、加賀藩の権威を感じさせる荘厳さがあります。また、楼門の背景には「朱色の鉄筋コンクリート造りの建物」という珍しい設計がなされており、近代的な要素と伝統的な神社のスタイルが見事に融合しています。この門は、1900年に建設され、金沢の街並みに美しいアクセントを加える存在です。 また、尾山神社は四季折々の自然の美しさも魅力的です。春には桜が咲き誇り、特に本殿周辺は桜の名所としても知られています。初夏には新緑が美しく、秋には紅葉が見事な景色を作り出します。冬の雪景色もまた、静寂な美しさを醸し出し、訪れる人々に深い印象を与えます。自然と調和した神社の景観は、訪れる人々に癒しと平穏を提供しています。 尾山神社はまた、地域の文化やイベントと密接に関わっている場所でもあります。特に毎年行われる「尾山神社大祭」は、多くの参拝者で賑わい、地域の人々にとって重要な祭りとなっています。この祭りでは、神輿の巡行や伝統的な儀式が行われ、地域社会と神社とのつながりを感じることができます。 加えて、尾山神社周辺には観光スポットも豊富にあります。金沢の有名な観光地である兼六園や金沢城公園からも近く、これらと合わせて訪れることができます。また、尾山神社の境内には、前田利家公の銅像や歴史的な石碑もあり、歴史的な遺産を感じながら散策することができます。 尾山神社はその歴史的背景、見事な建築、自然の美しさ、そして地域の文化と密接に結びついた場所として、多くの人々に愛され続けています。
-
-

-

- 0枚
-
-

-

- 0本
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 金沢市本多町にある廣坂稲荷は、由緒ある神社で、地元住民や観光客に親しまれています。この神社は、金沢城や兼六園に近接する広坂地区にあり、周囲の豊かな自然と歴史的背景が調和した雰囲気があります。 廣坂稲荷の創建時期については、正確な記録が残っていないようですが、江戸時代以前に遡ると言われています。 金沢市本多町の地域は、江戸時代に加賀藩の拠点として発展しました。特に、金沢城が築かれた後は城下町として賑わい、廣坂稲荷もその繁栄に重要な役割を果たしていたようです。地元の人々は、稲荷神を地域の守護神として崇拝し、農業や商業の成功を祈願しました。 廣坂稲荷は、江戸時代から明治時代にかけて大きな信仰を集めましたが、金沢の都市化や社会変化に伴い、時代とともに役割も変化してきました。それでも、地元の人々は伝統を守り続け、現在でも多くの参拝者が訪れています。 廣坂稲荷の境内は、落ち着いた雰囲気に包まれています。神社の入り口には朱塗りの鳥居が立ち、稲荷神社の象徴的なデザインを引き継いでいます。この鳥居をくぐると、参道沿いに狛狐が配置され、神聖な空気が漂います。狛狐は稲荷信仰において重要な存在であり、稲荷神のお使いとされています。 本殿はシンプルながら美しい木造建築で、歴史の重みを感じさせます。境内には四季折々の自然が楽しめる植栽が施され、春には桜、夏には新緑、秋には紅葉、冬には雪景色と、訪れるたびに異なる表情を見せています。 金沢市を訪れる観光客にとって、廣坂稲荷は静かで落ち着いた観光スポットとして人気があり、兼六園や金沢城公園といった主要観光地から徒歩圏内にあることから観光ルートに組み込むのに最適です。 訪れる際には、参拝のマナーを守り、地域の文化や歴史に敬意を払うことが重要です。また、周辺には地元の飲食店やカフェも点在しているため、参拝後に金沢の食文化を楽しむのもいいと思います。 是非、金沢観光の際には訪れてみてください!
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 金沢在住の私が愛してやまないお寺の一つがこの「雨宝院」であり非常に歴史のあるお寺になります。今住んでいる私の家から徒歩で5分と掛からないところにあるお寺で非常に馴染みがあります。場所は金沢市で一番の繁華街の片町から徒歩10分掛からない程で、金沢の中心を流れる犀川に架かる犀川大橋のたもとの川沿いにあります。このお寺が有名なのは、金沢の文豪である「室生犀星」のゆかりのお寺であるからです。室生犀星が幼少期から養子として育てられたのがこのお寺で、境内には犀星ゆかりの遺品や直筆の小説原稿、再生が書いたお寺宛ての手紙などの多くの品々が展示されています。私の子供たちが通っていた金沢市中心部の「中村町小学校」の校歌も室生犀星の作詞で地元石川県だけでも小学校、中学校、高校、大学を合わせると12校もの校歌を作詞しています。雨宝院の場所周辺は金沢では有名な「寺町(てらまち)寺院群」と呼ばれ、戦災にあっていないその街並みは、江戸時代の雰囲気が良く残っている地域となっています。室生犀星の数ある小説の中でも、この雨宝院がしばしば登場し、有名なところでは「性に目覚める頃」では、抹茶を好んだ養父の手伝いで、寺院の裏手から雑賀の水を汲みに行った事や、その川の水が清らかで澄んでいる事、鮎やウグイが泳ぐ姿など、雨宝院から見る犀川の美しさが非常に細やかに表現されています。境内には「まよい小石」という大きな石があり、この石にもたれたりするのを犀星は好んでいたと言う話も有名で、小説の中では『子供が道に迷ったりすると、この墓碑に祈願すれば、ひとりでに子供の迷っている町がわかる』石、として紹介されています。犀星の作品から大正期の金沢を思い起こす事は容易で、雨宝院はその中でも目立つ様な大きなお寺でもなく、犀川の川べりにひっそりと寄り添っている感じなのであるが、だからこそ心静かに昔を回想してゆっくりとした時間を過ごすには非常に良いお寺であると思います。近くには「室生犀星記念館」もあるので「雨宝院」と併せて訪れてみる事をお勧めします。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 尾山神社は、石川県金沢市に位置する歴史的で文化的にも重要な神社で、観光地としても非常に人気があります。ここでは、尾山神社の魅力をいくつかの視点から紹介します。 まず、尾山神社は金沢の歴史に深く根ざした場所です。神社は、加賀藩初代藩主である前田利家公を祀るために創建されました。利家公は、豊臣秀吉に仕えた名将であり、加賀藩の礎を築いた人物です。神社には利家公とその妻であるまつ(まつ姫)の霊を鎮めるための本殿があり、歴史的にも重要な意味を持つ場所として、多くの参拝者が訪れます。 尾山神社の最大の魅力の一つは、その建築様式です。特に「尾山神社の楼門」は、金沢市の象徴的な建物の一つとして有名です。この楼門は、前田家のシンボルである「三つ葉葵」の紋をあしらったデザインが特徴的で、加賀藩の権威を感じさせる荘厳さがあります。また、楼門の背景には「朱色の鉄筋コンクリート造りの建物」という珍しい設計がなされており、近代的な要素と伝統的な神社のスタイルが見事に融合しています。この門は、1900年に建設され、金沢の街並みに美しいアクセントを加える存在です。 また、尾山神社は四季折々の自然の美しさも魅力的です。春には桜が咲き誇り、特に本殿周辺は桜の名所としても知られています。初夏には新緑が美しく、秋には紅葉が見事な景色を作り出します。冬の雪景色もまた、静寂な美しさを醸し出し、訪れる人々に深い印象を与えます。自然と調和した神社の景観は、訪れる人々に癒しと平穏を提供しています。 尾山神社はまた、地域の文化やイベントと密接に関わっている場所でもあります。特に毎年行われる「尾山神社大祭」は、多くの参拝者で賑わい、地域の人々にとって重要な祭りとなっています。この祭りでは、神輿の巡行や伝統的な儀式が行われ、地域社会と神社とのつながりを感じることができます。 加えて、尾山神社周辺には観光スポットも豊富にあります。金沢の有名な観光地である兼六園や金沢城公園からも近く、これらと合わせて訪れることができます。また、尾山神社の境内には、前田利家公の銅像や歴史的な石碑もあり、歴史的な遺産を感じながら散策することができます。 尾山神社はその歴史的背景、見事な建築、自然の美しさ、そして地域の文化と密接に結びついた場所として、多くの人々に愛され続けています。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 金沢在住の私が愛してやまないお寺の一つがこの「雨宝院」であり非常に歴史のあるお寺になります。今住んでいる私の家から徒歩で5分と掛からないところにあるお寺で非常に馴染みがあります。場所は金沢市で一番の繁華街の片町から徒歩10分掛からない程で、金沢の中心を流れる犀川に架かる犀川大橋のたもとの川沿いにあります。このお寺が有名なのは、金沢の文豪である「室生犀星」のゆかりのお寺であるからです。室生犀星が幼少期から養子として育てられたのがこのお寺で、境内には犀星ゆかりの遺品や直筆の小説原稿、再生が書いたお寺宛ての手紙などの多くの品々が展示されています。私の子供たちが通っていた金沢市中心部の「中村町小学校」の校歌も室生犀星の作詞で地元石川県だけでも小学校、中学校、高校、大学を合わせると12校もの校歌を作詞しています。雨宝院の場所周辺は金沢では有名な「寺町(てらまち)寺院群」と呼ばれ、戦災にあっていないその街並みは、江戸時代の雰囲気が良く残っている地域となっています。室生犀星の数ある小説の中でも、この雨宝院がしばしば登場し、有名なところでは「性に目覚める頃」では、抹茶を好んだ養父の手伝いで、寺院の裏手から雑賀の水を汲みに行った事や、その川の水が清らかで澄んでいる事、鮎やウグイが泳ぐ姿など、雨宝院から見る犀川の美しさが非常に細やかに表現されています。境内には「まよい小石」という大きな石があり、この石にもたれたりするのを犀星は好んでいたと言う話も有名で、小説の中では『子供が道に迷ったりすると、この墓碑に祈願すれば、ひとりでに子供の迷っている町がわかる』石、として紹介されています。犀星の作品から大正期の金沢を思い起こす事は容易で、雨宝院はその中でも目立つ様な大きなお寺でもなく、犀川の川べりにひっそりと寄り添っている感じなのであるが、だからこそ心静かに昔を回想してゆっくりとした時間を過ごすには非常に良いお寺であると思います。近くには「室生犀星記念館」もあるので「雨宝院」と併せて訪れてみる事をお勧めします。
-
-

-

- 0枚
-
-

-

- 0本
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 金沢市本多町にある廣坂稲荷は、由緒ある神社で、地元住民や観光客に親しまれています。この神社は、金沢城や兼六園に近接する広坂地区にあり、周囲の豊かな自然と歴史的背景が調和した雰囲気があります。 廣坂稲荷の創建時期については、正確な記録が残っていないようですが、江戸時代以前に遡ると言われています。 金沢市本多町の地域は、江戸時代に加賀藩の拠点として発展しました。特に、金沢城が築かれた後は城下町として賑わい、廣坂稲荷もその繁栄に重要な役割を果たしていたようです。地元の人々は、稲荷神を地域の守護神として崇拝し、農業や商業の成功を祈願しました。 廣坂稲荷は、江戸時代から明治時代にかけて大きな信仰を集めましたが、金沢の都市化や社会変化に伴い、時代とともに役割も変化してきました。それでも、地元の人々は伝統を守り続け、現在でも多くの参拝者が訪れています。 廣坂稲荷の境内は、落ち着いた雰囲気に包まれています。神社の入り口には朱塗りの鳥居が立ち、稲荷神社の象徴的なデザインを引き継いでいます。この鳥居をくぐると、参道沿いに狛狐が配置され、神聖な空気が漂います。狛狐は稲荷信仰において重要な存在であり、稲荷神のお使いとされています。 本殿はシンプルながら美しい木造建築で、歴史の重みを感じさせます。境内には四季折々の自然が楽しめる植栽が施され、春には桜、夏には新緑、秋には紅葉、冬には雪景色と、訪れるたびに異なる表情を見せています。 金沢市を訪れる観光客にとって、廣坂稲荷は静かで落ち着いた観光スポットとして人気があり、兼六園や金沢城公園といった主要観光地から徒歩圏内にあることから観光ルートに組み込むのに最適です。 訪れる際には、参拝のマナーを守り、地域の文化や歴史に敬意を払うことが重要です。また、周辺には地元の飲食店やカフェも点在しているため、参拝後に金沢の食文化を楽しむのもいいと思います。 是非、金沢観光の際には訪れてみてください!
- 前のページ
- 1
- 次のページ
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本